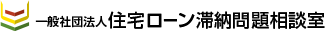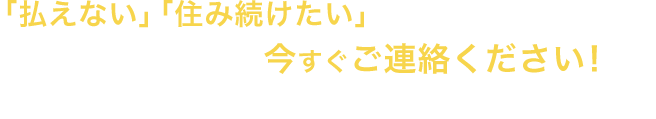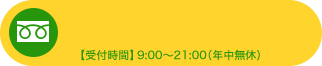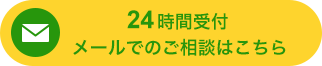リースバックで買戻しができる条件・買戻し時の価格は?

リースバックは、住宅ローンの支払いが難しい状況に陥り、家を手放さなければならないけれど今の家に住み続けたい場合や、一時的にまとまったお金が必要な場合などに検討される方法です。リースバックでは、自宅を売却後に買い戻すことも可能ですが、確実に買い戻すためにはいくつか注意すべき点があります。
この記事では、リースバックで買戻しができる条件や注意点、リースバックの買戻し時の価格の相場、リースバックでよくあるトラブルなどについて詳しく解説します。
目次
1.リースバックの買戻しの基礎知識と注意点
リースバックを行っている不動産会社の多くは、将来的な買戻しを可能としています。まずは、リースバックで買戻したい場合に知っておきたい基本的な事項や注意点について説明します。
(1)買戻し価格は売却時よりも高くなる
リースバック後に自宅を買い戻す場合、以下のような流れとなります。
- 自宅を売却
- 新たな所有者と賃貸契約を締結して住み続ける
- 再購入(買戻し)
再購入の際の価格は、最初の売却時より高くなることが一般的です。
「ずっと家賃を払い続けてきたのに、売値で買い戻せないの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、買主である不動産会社や投資家は、ビジネスの一環としてリースバックを提供しています。そのため、利益を出すために売値に上乗せした価格で購入を求められるのです。
リースバック中に支払う家賃を、再購入のための積立だと勘違いされている方もいらっしゃるようですが、カーリースのように「〇年使用すれば購入価格が無料」とはなりませんので、注意してください。
(2)住宅ローンが利用できるケースも
リースバックに至った経緯にもよりますが、買戻しの際に住宅ローンが利用できるケースもあります。
任意売却を経た場合などは、信用情報機関に事故情報が登録されているため、住宅ローンの利用は難しいことが多いです。しかし、まとまったお金を得るためにリースバックを利用した場合など、信用情報に問題がないケースでは、住宅ローンを利用できる可能性があります。
ただし、長期間、賃貸契約で住み続けた後に買戻しをする場合、家の築年数や契約者の年齢などが問題となり、断られる可能性もあります。住宅ローンの利用を検討する際は、複数の金融機関に相談した上で、見込みのありそうな金融機関を厳選して申し込むとよいでしょう。
(3)買戻し特約と再売買の予約
リースバック契約で、買戻しについて事前に契約で定める場合、買戻し特約と再売買の予約という二つの形態があります。どちらも買戻しについてルールを決めておく点は同じですが、買戻し特約は以下のように当事者の制約が多いです。
- 売値以上の価格で再売買しなくてはならない
- 契約成立から10年以内に買い戻さなければならない
- 売買契約と同時に買戻し特約を設ける必要がある
このような事情から、実務上ではより自由に契約内容を決められる再売買の予約が利用されることがほとんどです。再売買の予約は、リースバック契約時に条件を定めて、将来的な再度の売買契約を約束しておくものです。
契約を解除することで物件を手元に戻す買戻し特約とは異なり、あくまで再度の売買契約なので、期間や価格などを自由に定めることが可能です。
2.リースバックで買戻しができる条件
実は、リースバックでは無条件に買戻しができるわけではありません。買戻しができる条件について説明します。
(1)事前に買戻しの約束をしている
確実に買戻したい場合、事前に買戻しについて約束しておく必要があります。事前の約束がない状態で買戻しを打診しても、所有者は売却を断ることができるからです。事前の約束がないと、第三者に転売される可能性もあります。
(2)家賃の滞納がない
リースバックの賃貸契約中に家賃を滞納すると、買戻しの約束を取り消されることがあるため注意が必要です。この点の対応は所有者によって異なりますが、厳しいところでは一度滞納しただけでも買戻しの約束を取り消されてしまうこともあります。家賃の引き落とし口座への入金忘れなどによる滞納をしないように注意しましょう。
(3)普通借家契約を選ぶ
リースバックの賃貸契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
普通借家契約は、借主の意思だけで更新できる契約です。一方で、定期借家契約は賃貸借期間が終了とともに契約が終了になるため、契約更新はできません。
定期借家契約のリースバックを選ぶと、リースバック会社が物件を第三者へ売却した場合、賃貸借期間が終了した時点で新たな貸主から退去を要請される恐れがあります。
買戻しのための資金調達に時間がかかることも踏まえ、リースバックの賃貸契約では普通借家契約を選ぶべきだといえます。
3.リースバックの買戻し時の価格の相場
リースバックで買戻しを希望している場合に、気になるのが買戻しの価格です。買戻価格がいくらになるかは物件によって異なりますが、相場の目安はあります。
(1)売却価格の1.1倍から1.3倍が相場
リースバックの買戻し時の価格は、売却価格の1.1倍から1.3倍程度になることが多いです。仮に1,500万円で売却したのであれば、1,650万円から1,950万円ほどになる計算です。
ただし、価格は、最初の売却価格、契約当初の不動産相場、立地による需要の高さなどにも影響されます。将来的に買戻しを検討するのであれば、リースバック契約前に見積もりを取ることをおすすめします。
(2)家賃と買戻価格のバランスに注意
買戻しを検討する際は、価格と家賃のバランスにも注意が必要です。家賃が高くなると、その分、家計への影響が大きくなるためです。「毎月の家賃を支払うのもやっと」という状態では買い戻すのも難しくなります。
リースバックにおいては、最初の売却価格と家賃、買戻し時の価格は全てつながっています。家賃も買戻し時の価格も、不動産会社は「仕入れ値(利用者から見た売却価格)の〇%」という形で評価するためです。契約前にそれぞれの金額の全貌を把握することが、買戻しのための資金計画を立てる第一歩となります。
(3)売却価格を抑えて買戻価格を安くできることも
不動産会社との交渉次第では、売却価格を抑えることで、将来的な買戻し時の価格を安くできる可能性があります。
例えば、「子供の進学費用が必要」など、売却する理由と金額が明確に決まっているとします。前述した通り、売却価格と家賃、買戻し時の価格は相関関係にあるため、最初の売却価格を必要な分だけに抑えることで家賃と買戻し時の価格を安くできることがあります。
高く売却した方がお得に思えるかもしれませんが、リースバックでは、あえて価格を抑えて売却した方が将来的な負担を抑えられることもあるのです。
4.リースバックの買戻しの際にかかる費用
リースバックの買戻しの際は、自宅を買戻す費用だけではなく、その他にもさまざまな費用が発生します。リースバックの買戻しの際に必要な費用について説明します。
(1)登録免許税
登録免許税は、不動産の所有権の転移のための登記情報を申請する際にかかる税金です。
買主が所有権移転を行うため、リースバックの買戻しの際には登録免許税を負担しなければなりません。
登録免許税は、不動産の固定資産評価額によって金額が変動します。
住宅の場合は軽減税率の対象になるため、役所に証明書を提出しましょう。
(2)司法書士の手数料
リースバックの買戻しでは、所有権移転登記や抵当権設定登記などの手続きが必要です。
こうした手続きは司法書士に依頼することが一般的であり、依頼すれば費用が発生します。
司法書士の費用は、ローンを利用しない場合で5~10万円、ローンを利用する場合で10~15万円が相場です。
(3)印紙税
不動産の売買契約書には収入印紙を貼り付ける必要があり、その費用を印紙税といいます。
印紙税は売買価格によって異なり、1万円以下は非課税になりますが、それ以上の価格の場合は以下の金額が発生します。
| 不動産売買価格 | 本則税率 | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 1万円以上10万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円以上50万円以下 | 400円 | 200円 |
| 50万円以上100万円以下 | 1000円 | 500円 |
| 100万円以上500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
| 500万円以上1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
| 1000万円以上5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5000万円以上1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円以上5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
| 5億円以上10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
| 10億円以上50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
| 契約金額の記載がないもの | 200円 | 200円 |
(4)事務手数料
リースバックの業者によっては、買戻し条件として買戻し費用とは別に事務手数料が設定されている場合があります。
事務手数料の相場は、買戻し価格の1~3%程度です。
事務手数料が無料のリースバック業者もあるため、リースバックの契約時に買戻し予約を設ける際に確認するようにしましょう。
(5)ローン保証料や手数料
リースバックの買戻しで住宅ローンを利用する場合には、借入先となる金融機関へのローン保証料や手数料が発生します。
金融機関ごとに金額の設定は異なるため、ローンを利用する際には複数の金融機関を比較して検討しましょう。
5.リースバック後の買戻しを確実に実現するためのポイント
リースバック後の買戻しでは、売却価格よりも高値になってしまうことが一般的です。
売却価格よりも高値になることは仕方ないとしても、買戻しをしたいタイミングがきた時に高額すぎて買戻せないという事態は避けたいところです。そのためのポイントについて説明します。
(1)買戻せる価格に買取価格を設定する
売却時に買い戻すことを決めている場合は、買戻しのタイミングは自由で、買取価格は固定という契約を締結することが理想的です。その際、買取価格は将来的に買戻しできる金額に設定します。
そのようにしておけば、買戻しの際に予想外に高額で買戻しができないという事態を回避できます。
(2)買戻しのための資金は計画的に確保する
リースバックにおける買戻しでは、住宅ローンを組めるとは限りません。借金の滞納など信用情報に事故情報が登録されていれば、住宅ローンの審査は通らない可能性が高いです。
住宅ローンが組めない可能性を考慮して、計画的に買戻しのための資金を確保しましょう。
(3)付帯条件を確認する
確実に買戻しをするためには、付帯条件についてもしっかりと確認することが重要です。
付帯条件とは、「敷金・礼金なし」「保証人の必要なし」「原状回復の必要なし」など、付帯する条件のことをいいます。
付帯条件の内容によっては不利になってしまうこともあります。例えば、敷金や礼金がある場合、初期費用が高くなってしまいます。
買戻す場合には原状回復については気にする必要はありませんが、買戻さずに将来的に退却する可能性もあるなら、修繕範囲や費用に関する取り決めはあらかじめ行っておくべきです。
(4)不動産会社を複数比較する
リースバックを依頼する不動産会社を選ぶ際には、複数の会社を比較することをおすすめします。
売却価格が異なるだけではなく、買取価格の設定や付帯条件など、不動産会社によって異なる部分は多いです。
ネット上の口コミなどから判断するのではなく、不動産会社の公式サイトで実績を確認したり、複数の会社に見積りを依頼して条件を比較したりすることも大切です。
不動産会社選びで失敗して後悔することがないように、納得できるまで比較検討してみてください。
6.リースバックでよくあるトラブル
インターネット上には「リースバックは怖い」「詐欺ではないのか」などという声もあります。リースバックは、不動産会社が契約や法律に違反せずともトラブルに発展する事例がしばしばあります。典型的なトラブルの事例を紹介します。
(1)物件を転売されて持ち主が変わる
リースバックの物件を購入した所有者は、賃借人(入居者)の許可を得ることなく、自由に物件を転売することができます。
転売前の所有者と交わしていた契約は、新しい所有者にも引き継がれるため、通常は特に問題が起きることはありません。しかし、契約について口約束で合意していた内容があると、新しい所有者に引き継がれず、トラブルの種になることがあります。
このようなトラブルを防ぐためには、契約内容は全て契約書に記載し、転売された際にも全て引き継がれるようにしておくことが大切です。
(2)所有者が買戻しに応じない
所有者が買戻しに応じず、トラブルに発展するケースもあります。これは、「お金が溜まったら買戻します」などと口頭で約束している場合に起きるトラブルです。
法律上は口頭でも契約は成立しますが、契約の存在を示す証拠がないと、反故にされても責任を追及することができません。将来、買戻しを希望する場合は、必ず契約前に合意し、具体的な条件を契約書に記載しておきましょう。
(3)買戻しの時の価格が当初の約束と違う
買戻しの際に、当初の価格より高値を提示されるというトラブルもあります。
これは、リースバック契約の時点で、買戻し時の金額を決めておかなかったことが原因といえます。仮に口頭で合意していても「不動産相場が上がったので価格が変わります」などと言われれば対処する術がありません。
買戻しをするための資金計画を立てるためにも、事前に買戻し時の価格を決めておくことは非常に重要です。転売のリスクも考慮すると、価格を決めて契約書に記載しておくことが大切です。
(4)更新時に退去を迫られる
リースバックでは賃貸の契約形態によって住める期間が異なります。この点を理解せずに契約してしまうと「長く住みたかったのに追い出されてしまった」というトラブルに発展する可能性があります。
賃貸借契約の形態には、普通借家契約と定期借家契約の二つの種類があり、それぞれ以下のように契約内容が異なります。事前に契約内容をしっかり確認しておくことが大切です。
| 普通借家契約 | 定期借家契約 | |
| 更新の有無 | 更新が前提 | 原則として更新はなし(再契約で実質的に更新することはある) |
| 契約期間 | 2年程度(更新を繰り返して長期居住できる) | 2年程度(期間満了後は原則として退去する) |
| 賃借人の保護 | 賃借人からはいつでも退去の申し入れができる。所有者からの解約申し入れは制限される。 | 契約中の退去は原則としてできず、違約金の対象となることもある。契約満了時は無条件で退去となる。 |
7.リースバック以外の選択肢
住宅ローンの支払いが難しくなったけれど自宅を手放したくないという場合の選択肢はリースバックだけではありません。
リースバック以外の対処法もあるので、状況に応じて検討してみてください。
(1)親族間売買
親族間売買とは、親子や兄弟姉妹同士などの親族間で不動産売買を行うことです。
買主となる親族の同意を得られれば、リースバックと同様に住み続けることができます。
親族間売買には、柔軟性の高い取引ができるというメリットがありますが、税務署から、みなし贈与だと判断されないように注意が必要です。
(2)個人再生の住宅ローン特則
住宅ローンだけではなく他の借金の返済にも困っていて自宅を手放したくないという場合は、個人再生の住宅ローン特則を利用するという選択肢があります。個人再生とは債務整理の一種で、裁判手続きによって債務を大幅に減額することができます。
個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンはそのまま返済を続けられます。
債務整理なので新規借入やクレジットカードの作成などは一定期間できなくなりますが、返済負担が大きい場合には有効な方法といえます。
8.まとめ
多くのリースバック会社が、将来的な買戻しを可能としていますが、買戻しについてはトラブルも多いため、注意が必要です。
将来、買戻しを希望する際は、必ず契約前に所有者と詳細を協議し、決定した事項を契約書に明記することが大切です。特に、再売買の予約と、買戻し時の価格は重要なポイントとなります。
リースバック契約を検討中で、契約内容に不安をお持ちの場合は、リースバックの専門知識を持つ不動産会社に相談するとよいでしょう。
当社は、多くのリースバックや任意売却を手掛けてきた住宅ローン滞納問題を専門的に扱う不動産会社です。ご相談者様の状況やご希望を丁寧にお伺いした上で、最適な解決方法をご提案します。リースバック契約に関するご相談にも数多く対応しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一