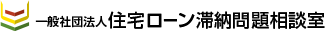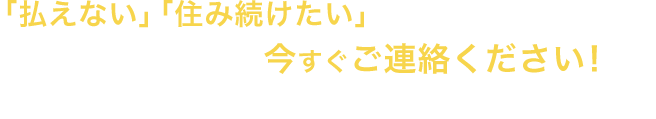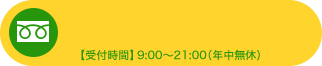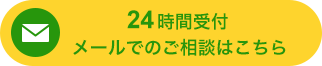親族間売買・親子間売買で「税金」はかかるのか?課税を回避する方法も解説
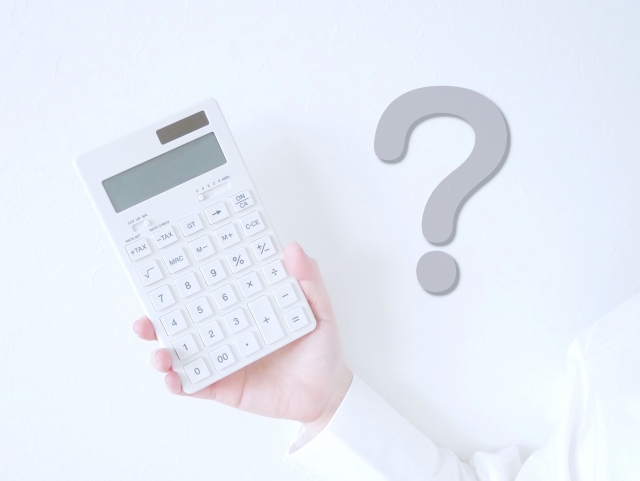
親族間売買・親子間売買をする際に税金がかかるのか?税金がかかるとすればどのくらいの税金がかかるのか?疑問に思っている方が多いのではないかと思います。
確かに、親族間売買が贈与税の対象となることはあります。ただし、それは一部の条件を満たす場合のみです。
この記事では、親子間売買・親族間売買でかかってくる可能性のある「税金」や、課税を回避する方法について解説していきます。
目次
1.親族間売買・親子間売買とは?
親族との間で不動産を売買することを「親族間売買」、親子間で不動産を売買することを「親子間売買」と呼びます。
特に「親子間売買」の場合は、子は親が亡くなったときに、基本的には不動産を相続できるので、特別な事情がない限り売買することはないため、一般の不動産の売買 に比べると稀になります。
(1)ローンを組むことができるのか?
まず、親族間売買・親子間売買ローンを組むことは可能ですが、一般的な住宅ローンを組むよりもハードルは高くなります。
ハードルが高くなる理由としては、融資をする銀行が、売買ではなく、贈与という認識になるため、そもそも融資をしてくれる銀行が少ないのです。上記に述べた通りいずれ相続できる不動産をなぜ売買するのか、相続税逃れのための売買ではないかと疑われるため、大手の銀行は、まず融資をしてくれません。窓口で断られてしまうでしょう。限られた金融機関のみが、親族間売買・親子間売買の融資をしてくれます。
弊社では、この限られた金融機関と取引があるため、他社で断られた案件でも融資を受けることができ、無事に親族間売買・親子間売買ができたという事例が多くあります。
次に、融資をしてくれる銀行が見つかったとしても、思うような融資額を受けることができないことがあげられます。
例えば、2,000万円のローンを組んで、2,000万円で不動産を売買しようと検討していたが、提示された融資可能額は1,500万円であった等。
ローンを完済していれば、1,500万円で売買をすることをできますが、残債が2,000万円残っているとなると差額の500万円を用意しないと売買をすることはできません。
市場性があるエリアであれば、希望の融資額を借入することができるかもしれませんが、不動産の売買自体が活発ではないエリアとなると融資自体が難しいこともあります。
(2)親族間売買・親子間売買の注意点
相続人が複数いる場合は、注意が必要です。例えば、実家を長男が相続で取得するつもりだったが、次男が長男に何の相談もせずに親子間売買をしてしまう等、後々のトラブルになることもあります。
また、子がローンを組んだその後、独立して他の不動産(戸建やマンション)を購入するときに既にローンを組んでしまっているために、ローンが通りづらいということもあるので家族間で良く話し合うことが必要です。
2.親族間売買・親子間売買で「税金」がかかるのか?
不動産の売買では、様々な税金がかかります(不動産取得税・登録免許税・印紙税・譲渡所得税等)。
こちらでは4つのパターンに分けて解説していきます。
(1)親子間売買・親族間売買で「高い価格」で売買した場合
この場合、売主が不動産を売却することによって、キャピタルゲイン(売買差益)が出た場合、譲渡をしたことによって利益を得ているため、売主は「譲渡所得税」がかかります
買主は、利益の出る高い金額で購入しているため、贈与税はかかりません。
(2)親子間売買・親族間売買で「通常の価格」で売買した場合
不動産を売却して利益がない場合、譲渡所得税はかかりません。また利益がでたとしても自己居住用の不動産の場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が利用できるため、譲渡所得税はかかりません。
買主も、通常の価格で購入しているため、贈与税はかかりません。
(3)親子間売買・親族間売買で「著しく低い価格」で売買した場合
売主は低額で売却して利益が出ない場合、譲渡所得税はかかりません。
しかし、買主は市場価格よりも安い金額で買い受けているため、「贈与税」が課されます。
この場合の贈与税を、「みなし贈与」とも呼びます。
例えば、通常4,000万円が相場のマンションを、親族に1,500万円で売却したとします。この場合、相場との差額である2,500万円は贈与となるため、贈与税の対象となります。
細かい計算を省いた概算ですが、一般贈与のケースであれば、基礎控除100万円と控除額250万円を除いた2,150万円に、税率の50%をかけて計算します。この場合、支払う贈与税は1,075万円となります。
このように、税務署は不動産取引の売買価格をしっかりと確認しているため、思わぬ税金を課税されないためには対策が必要です。
(4)名義変更のみを行う場合
親子間売買・親族間売買ではありませんが、土地や建物の名義変更のみを行うようなケースもあるでしょう。
不動産の名義だけを変更し、実質的な家の主人が変わらない場合でも、対価のやりとりがなければ贈与となります。
例えば、不動産を所有している高齢者の中には「死んでから迷惑をかけないよう、生きているうちに子供に名義だけでも変更しておきたい」と考える方もいらっしゃいます。気持ちは理解できるのですが、税務署から見ると、金銭のやりとりのない不動産の名義移動は贈与そのものです。
「とりあえず」という考えで名義変更を行い、贈与税の請求をされないように注意しましょう。
3.なぜ、贈与税がかかるのか?
不当に安い金額で売買(低廉売買)した場合、売買ではなく、贈与と判断されてしまうと贈与税がかかってきます。
例えば、相場が2,000万円の不動産を1,000万円で子供に売却したとすると確かに1,000万円で売却はしているのですが、1,000万円市場価格より安く売買しているため、1,000万円の贈与があったものと見なされてしまうのです。
それでは、贈与税がかかる場合、どれくらいの税金がかかるのかみていきましょう。
国税庁が贈与税の早見表を公開しています。
上記例と同じく、相場2,000万円の不動産を1,000万円で子供に売却して1,000万円の贈与とみなされた場合、早見表を基に計算すると一般贈与財産と特別贈与財産によって税率は異なります が、一般贈与財産の場合231万円、特別贈与財産の場合177万円の税金がかかってきます。
特別贈与財産とは、親や祖父母から20歳以上の子供や孫へ贈与のことをいい 、一般贈与財産より税率が低く設定されています。一般贈与財産とは、特別贈与財産以外の贈与財産のことをいいます。
「親子間売買」の場合は、特別贈与財産となるので177万円の贈与税がかかります。
4.税金がからない方法とは?
親子間売買・親族間売買で税金がかからないようにするには、次の2つの方法のどちらかを採用すべきだといえます。
(1)適正価格で売買
贈与税がかからない方法は、市場価格に近い金額で売却するほかありません。目安としては、固定資産税の評価証明書や戸建であれば路線価、公示価格が参考資料として有効になります。ただ、 いくらで売買すれば低廉売買に当たらない等の指針がないため、売買金額をいくらに設定するかは一般の人には難しい判断となります。
適正価格の判断ができない場合は、次の方法で対処しましょう。
①不動産鑑定を依頼する
不動産鑑定士に依頼して、不動産の価値がどの程度なのか調査する方法があります。不動産鑑定は、不動産鑑定士の有資格者が独占的に行う物件評価のことで、依頼者が報酬を支払って行います。
不動産の価格を知る方法としては、最も信頼性が高いとされており、万一税務署から贈与の疑いをかけられた場合に、価格の根拠として鑑定結果を提示することができます。
ただし、鑑定依頼には最低でも20万円程度の報酬が発生します。経済的に苦しい状況にある場合、大きな負担となるでしょう。
②専門知識の豊富な不動産会社に相談する
もう一つの方法は、親族間売買の経験が豊富な不動産会社に相談することです。不動産鑑定士の鑑定とは異なりますが、不動産会社は物件の査定を行うことが可能だからです。
不動産会社の査定では、「実際に不動産市場で買い手を探した場合、どの程度の金額になるか」という観点から調査を行います。親族間売買の対象物件も、市場で売却したケースを想定して価格の算定が行われるため、市場価格に近い価格を知ることができます。税務署が贈与かどうか判断する際は、市場相場との乖離の有無を基準とするため、これは大きなメリットといえるでしょう。
また、不動産鑑定士に鑑定を依頼した場合と違い、報酬が発生しないので、費用を節約したい方にもおすすめです。
(2)相続時精算課税制度
親族間売買で贈与税がかかるのを回避するために、相続時精算課税制度を利用できるのではないかと思われる方もいらっしゃるようです。
相続時精算課税制度とは 、60歳以上の親や祖父母が20歳以上の子供や孫に財産を贈与する際に、2,500万円までは贈与税を非課税にするという制度です。しかし、相続時精算課税制度とは、贈与をするときは非課税になるが、相続時には、非課税にした分もまとめて相続税を課税されるため、課税を回避するのではなく、先送りするだけとなる点に注意が必要です 。
相続時精算課税制度については、「相続時精算課税制度とは?親族間売買でも利用できる?」にて詳しく解説しておりますのでご参照ください。
5.親族間売買の仲介は不動産会社に依頼しましょう
親族間売買を検討する際、「売却先を探さずに済むので仲介は必要ない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、親族間売買を不動産会社に依頼することには大きなメリットがあります。主なメリットについて説明します。
(1)不動産の知識がなくても贈与税の課税を回避できる
先ほど解説したように、親族間売買では、売却価格が相場より大幅に安い場合、差分は贈与税の課税対象となります。そのため、市場相場に近い価格で売却することが重要なのですが、売買当事者だけで適正価格を算出することは可能でしょうか。
不動産の査定にはいくつもの要素が複雑に絡み合っており、知識のない一般の方では算出が難しいのが現実です。その点、不動産会社に依頼しておけば、価格査定を全て任せることができます。
自分に十分な知識がない場合でも、適正価格を知り、贈与税の課税を回避できるのは、不動産会社に依頼する大きなメリットといえます。
(2)住宅ローンを利用しやすくなる
不動産会社への依頼をおすすめするもう一つの理由は、住宅ローンの審査に各段に通りやすくなることです。
親族間売買では、住宅ローンを利用できない点が問題となることが多いです。これは、住宅ローンの貸付を行う金融機関が、親族間売買希望者への融資を敬遠するためです。メガバンクであればまず断られますし、地方銀行・信用金庫でもごく一部の金融機関しか取り扱っていません。
これは、金融機関から見て、親族間売買では、住宅購入以外の用途に貸付金を利用されるリスクがあるためです。資金を不正に利用されても、当事者間で口裏を合わせられると、金融機関には確認する術がありません。住宅ローンの貸付を断られた結果、金利の高い多目的ローンを利用するなど、不利な方法での資金調達を余儀なくされることがあります。
親族間売買の実績が豊富な不動産会社を通すことで、金融機関から一定の信用を得られます。また、不動産会社が提携している金融機関の住宅ローンを利用することも可能です。当事者のみで親族間売買を進めているケースと比べると、ぐっとローン審査に通りやすくなるのです。
6.まとめ
親子間売買・親族間売買でかかる可能性のある税金と、税金がかからないようにする方法について解説しました。
不動産売買に当たって税金は付き物ですが、親子間・親族間で低廉売買をして余分な税金がかかってしまうのはあまりにも勿体ないことです。
親族間売買・親子間売買で贈与税の課税を回避するためには「適正価格で売買を行うこと」がカギとなります。不動産に関する専門知識の乏しい一般の方が個人で査定を行うことは難しいため、親族間売買の実績が豊富な不動産会社に、査定を依頼することをおすすめします。
当社の初回相談では、まず相談時点での状況とご希望について確認させていただきます。その上で、3,000件以上の実績から得た経験をもとに、相談者様にとって最善の結果となるような解決策を提案させていただきます。事前に用意していただく書類もなく、相談料やコンサルタントフィー等もかかりませんのでお気軽にご相談ください。

クラッチ不動産株式会社代表取締役。一般社団法人住宅ローン滞納問題相談室代表理事。立命館大学法科大学院修了。司法試験を断念し、不動産業界に就職。住友不動産販売株式会社・株式会社中央プランナーを経て独立、現在に致る。幻冬舎より「あなたを住宅ローン危機から救う方法」を出版。全国住宅ローン救済・任意売却支援協会の理事も務める。住宅ローンに困った方へのアドバイスをライフワークとする。
監修者: 井上 悠一